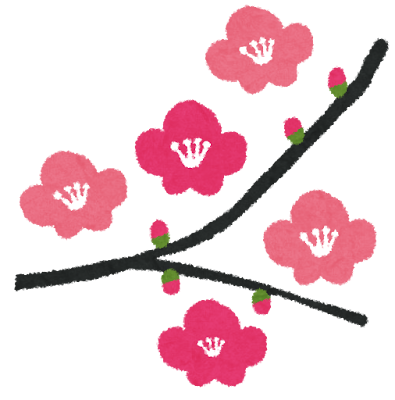俳句の心は、「梅は香がいのち、桜は散って行く様」というもの。
そのことを俳句結社「花鳥」の坊城俊樹主宰がラジオで語っていました。
このテーマについて、今回はエッセイ風にまとめて見ました。
梅は香、桜は散っていく様
先日、散歩していたらお寺の境内の梅が満開だったのが塀の向こう側に見えた。
思わずスマホで写真を撮った。
撮れた写真を見たら、塀で見えなかったところまで写っている。
よく見るとそのまた向こうに塀がある。
どうもお寺の境内ではなかったらしい。
見事な枝ぶりだった。
以前、丹沢の山に登って厚木の広沢寺温泉に下ってきたことがある。
さらに少し行くと十数本の梅が咲いていた。
けれどそのときは、その梅が見える前からその先に梅が咲いていることが分かった。風に乗り漂ってくる梅の香りはそれほど強烈だった。
初めほんのりと匂っていただけだったが、カーブを曲がるたびに香りが強くなっていき、そのうちにその梅が目に入る。
白梅だった。
それよりもずっと前のこと、湯河原の梅林に写真を撮りに行ったことがある。
まだフィルムカメラを使っていた頃だ。
そのとき古いカメラに凝っていて、このときはゼンザブロニカS2という6X6サイズのカメラを持って行った。
レンズ交換できるカメラなのだけれど、その時は標準のニッコールP75mmF2.8というレンズしか持っていなくて、梅林の中を何度も行ったり来たりして写真を撮った。
この梅林は山の斜面にあり、道は梅林の中をくねくねとうねるようについている。
このときは、残念ながら撮影に夢中で梅の香の記憶は残っていないが、梅林の中を抜ける曲線を描く山道が梅にとてもよく似合っていたという印象が残っている。
写真の方はといえば、2つ持っていたマガジンの片方に光線漏れがあり、半分はダメにしてしまった。
もう一台持って行った一眼レフのオリンパスM –1(のちにOM-1となる機種)の方は、シャッター速度がおかしくなっていることに気づかず。撮った写真はすべて露出オーバーでポジフィルムの向こう側が透けて見えた。
こうした失敗の思い出がある湯河原の梅林であるが、純粋に梅の香を楽しみに改めて訪れたい場所である。
先日、かわさきFMの「アキラのかなり最高(ハート)」という番組に、俳句結社「花鳥」主宰の坊城俊樹さんが出演された。
昨年、句集『壱』を出版され、その中の次の梅の句が紹介されていた。
白梅の香とて抱きぬ自づから
季題で梅というのは香、花といえば桜で目で見るもの。
梅というのは香りを嗅ぐというのが趣旨。
だから白い梅は白い香りがするのではないか。
紅梅なら赤い香りなのか甘い香りなのかわからないが、白梅は白い香りを梅自身が抱いているのじゃないか、白梅の存在というのは自分の白い香りを抱いているんだよという、そういう句だと作者自身の説明があった。
そして、「梅は香りがいのち、桜は散って行く様」だというのである。
昔は花といえば梅だった。それが平安の頃から桜に変わった。
確かに梅は香りがいい。
香りの記憶というものはどこか身体の奥深くまで染み込んでいき、再びその香を嗅ぐと、その時の様々な思い出が蘇ってくるという不思議な鍵だ。
初めに書いた私の体験がそのいい例だ。
桜の場合、匂いというよりもあの豪華さや華やかさと、それが去って散り始めたときの寂しさ、侘しさが背中合わせになっている。
そしてそれは視覚によるものだ。
桜といっても色々な種類を全て知っているわけではないが、この華やかな桜というのは、山桜などのしとやかな桜ではなく、ぱっと咲きぱっと散るソメイヨシノをイメージしている。多くの人がよく目にし、よく目立つゆえである。
そしてなぜか、桜が散り始めるまでの時の短さと散り始めてからの長さを思う時、人生と結びつけ哀愁に浸ることに快感を覚えるのである。
華やかな時は一瞬であることを皆よく知っている。
梅は香、桜は散って行く様というのは梅は嗅覚、桜は視覚、あるいは梅は鼻、桜は眼(まなこ)といいかえることができるだろう。
梅の香りは心を癒してくれる。
桜は心が穏やかでないとその美しさを感ずることができない。
そして、散る桜は高揚した心を鎮め、もののあわれや物寂しさを感じている自分に酔うことができるのである。
かわさきFMのその番組では、視聴者からのハガキの質問で、「散歩をしていて美しい雲や夕日に出会った時、さらりと一句作るにはどうしたらよいでしょうか」というものがあった。
これに対し坊城俊樹さんは、「俳句は頭の中だけでは作れません。外に出ることです。そして焦点を絞ってつくる。絞らないと俳句は作れません。漫然と歩いているだけではいつまでたっても俳句はできません」と答えていた。
コロナによる緊急事態宣言などもあり、句会が中止になったりしたのをいいことに、つい俳句を作るのをサボっていたら、なかなか句が作れないようになってしまった。
神経の伝達が鈍くなっているのだろう。ちゃんとまじめに句を作って神経回路の流れをスムーズにしておく必要がありそうだ。
では、このへんで
句集 壱 | 俊樹, 坊城 |本 | 通販 | Amazon
広告